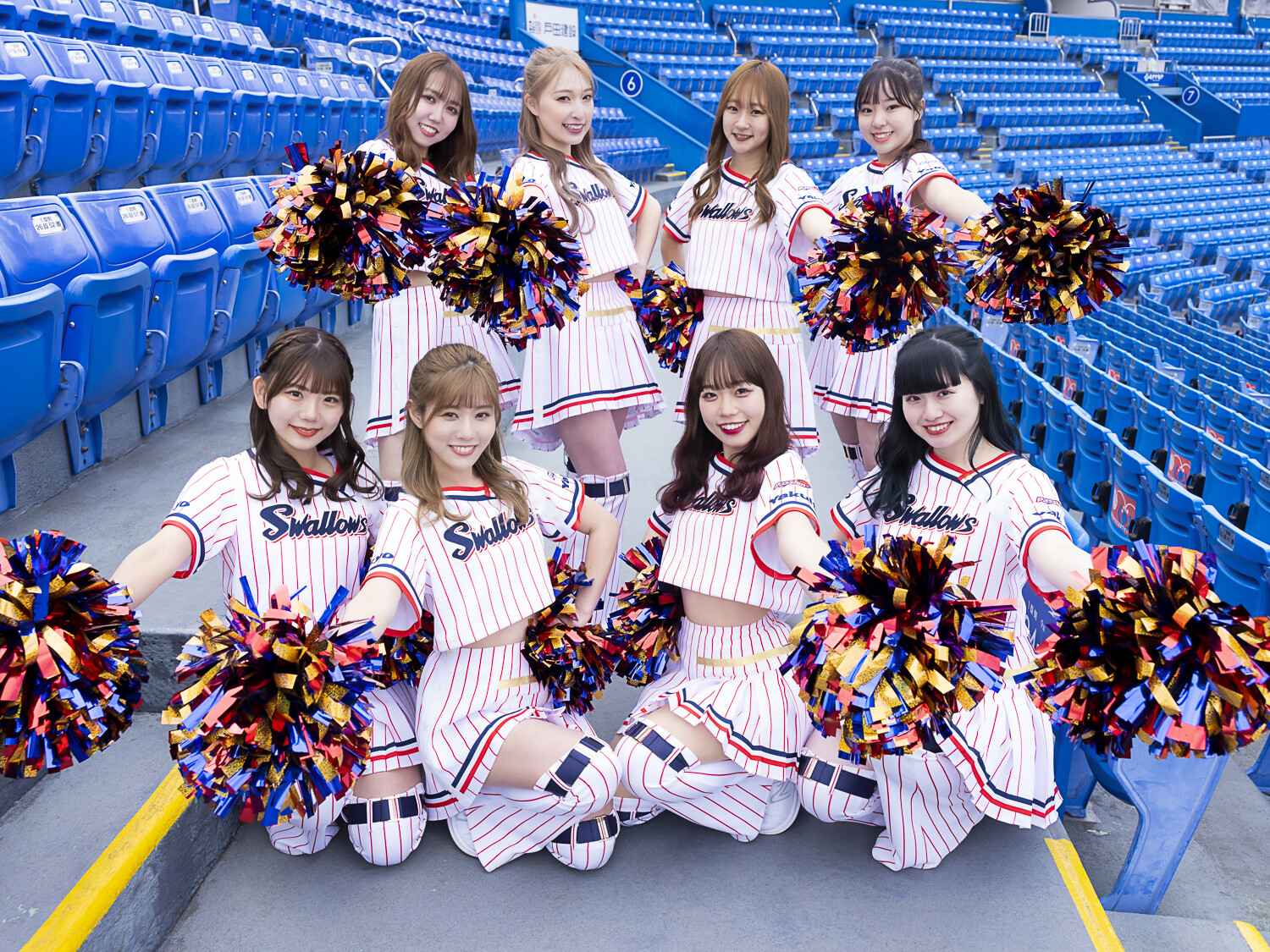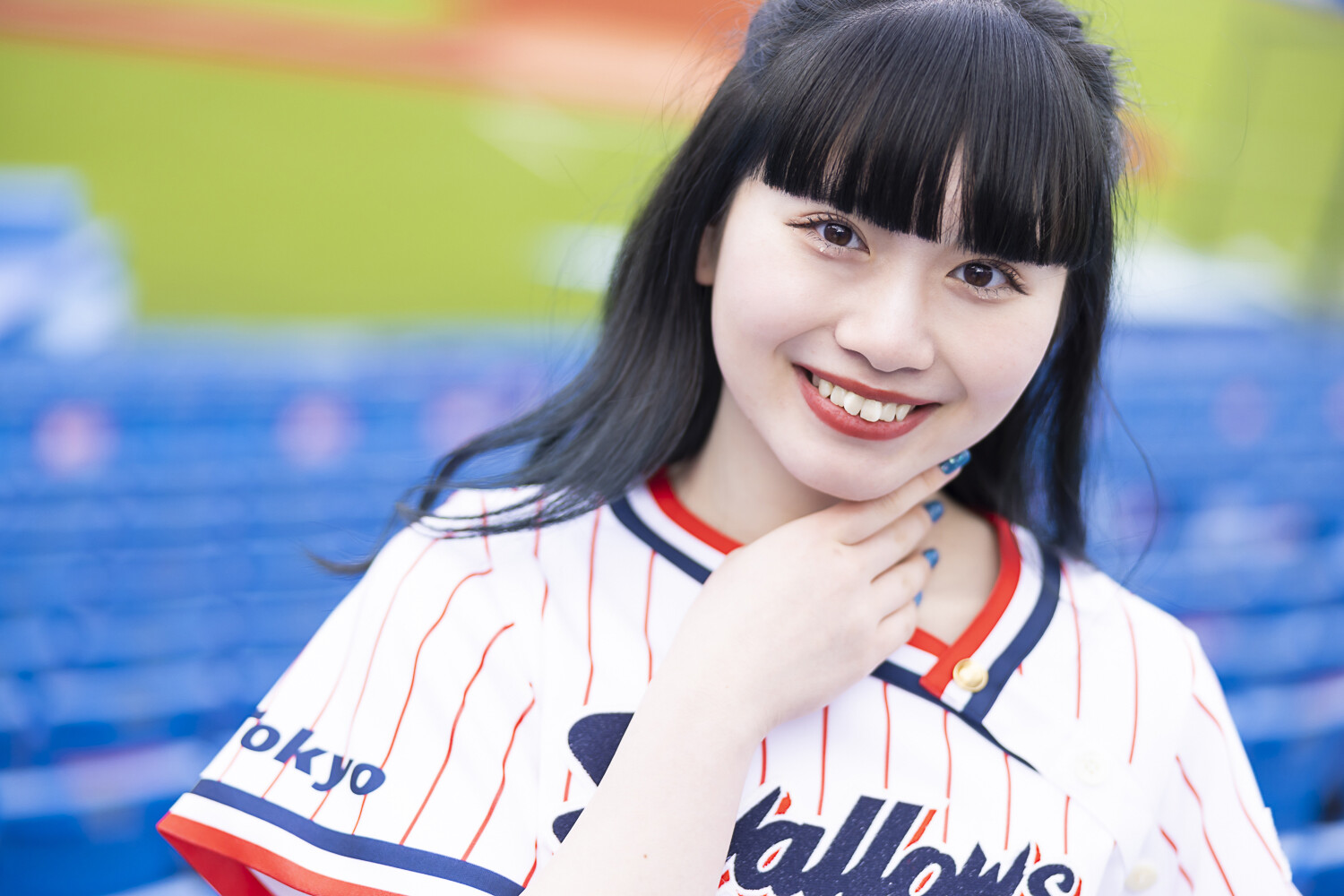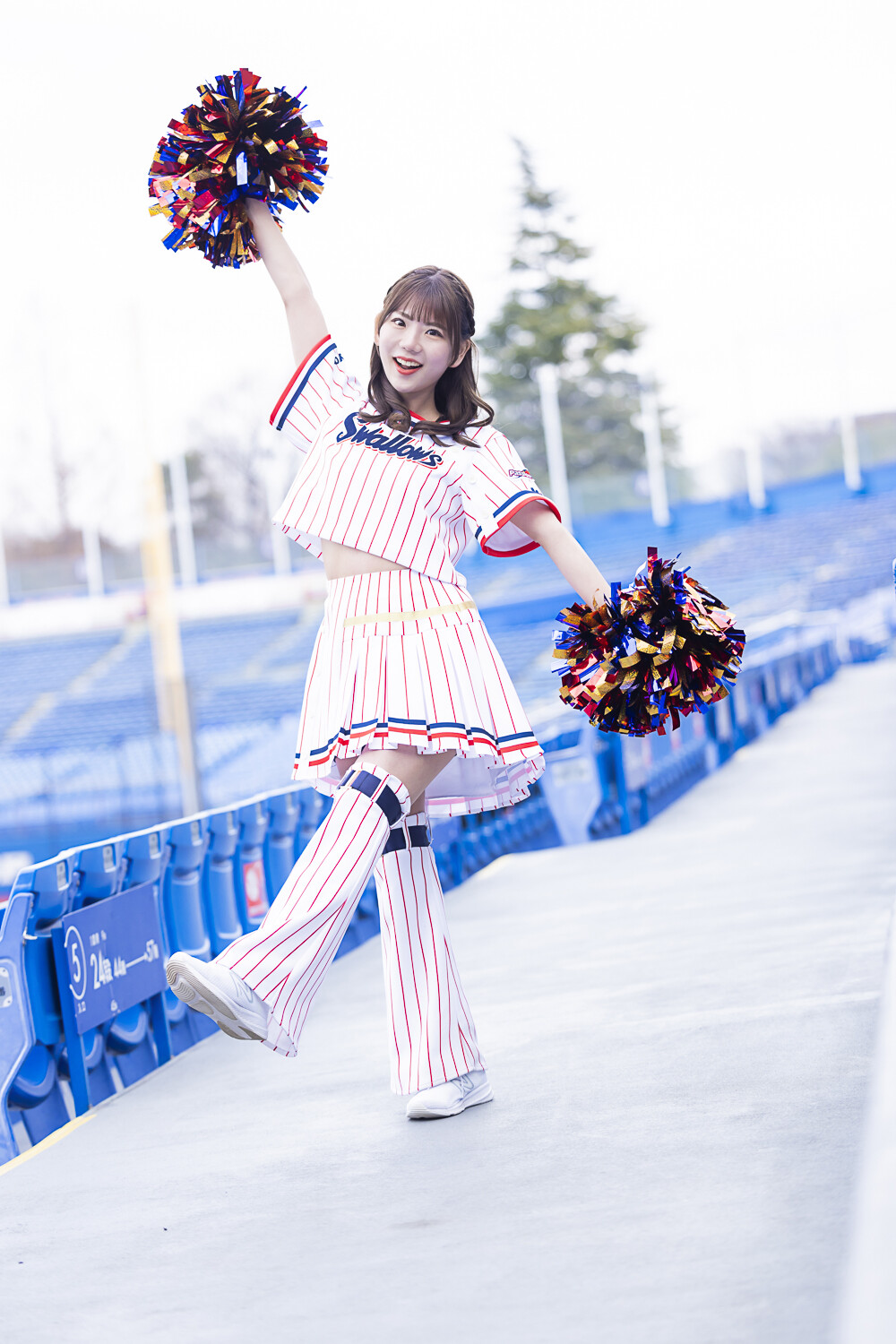ヤクルト原樹理が「心が折れたことは何回あったかわからない」から694日ぶりに一軍登板を果たすまで
8月27日、神宮球場。ヤクルト・原樹理が巨人戦でリリーフ登板し、694日ぶりに一軍マウンドに戻ってきた。岡本和真にホームランこそ許したが、力強いストレートを武器に2イニング1失点で復帰登板を終えた。
「準備もいつも通りにできましたし、頭の中も真っ白にならず、緊張もあまりしなかった。本当にいつもとおりだったんですけど、試合が終わって車で家に帰る途中くらいに、この2年が長かったことを感じました」
 8月27日の巨人戦で694日ぶりに一軍のマウンドに上がったヤクルト・原樹理 photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る
8月27日の巨人戦で694日ぶりに一軍のマウンドに上がったヤクルト・原樹理 photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る
【投げることがストレスだった】
2022年シーズン、原は自己最多となる8勝を挙げ、チームのリーグ連覇に貢献。しかし翌年は、上半身の故障の影響で「状態がよくなってくると何ががあるということが続いて......。本当に痛みとの戦いでした」と、険しい道のりを歩いていくことになるのだった。
2023年は開幕二軍スタート。徐々にイニング数を増やしていったが、100球を予定していた試合で2回降板。翌日、小野寺力投手コーチと長く話し込む光景が記憶に残っている。
「あの時期は野球をしている感じではなかったですね。腕を振っているつもりで投げても、指にボールの重みを感じないかというか、ボールが死んでいました。上体を気にして下半身が使えなかったし、投げていて何の収穫もなかった。どうしたら痛みが引くのか、いろんなことを試したんですけど変わらない。毎日、拷問を受けているようでした」
それでも「前に進まないといけないので......」と、戸田球場で練習を続けた。
「人間って、朝起きて歯磨きをして顔を洗うというのが一日の始まりじゃないですか。僕たちピッチャーにとっては、キャッチボールがそれなんです。それに対して『あー、キャッチボールかぁ。つらいな。今日は大丈夫かな』みたいな。そういう気持ちがある時点でしんどかったです。そこにピッチングがあるとなったらもっときますし、試合で投げるとなったらさらにくるんですよ」
1 / 4
著者プロフィール
島村誠也 (しまむら・せいや)
1967年生まれ。21歳の時に『週刊プレイボーイ』編集部のフリーライター見習いに。1991年に映画『フィールド・オブ・ドリームス』の舞台となった野球場を取材。原作者W・P・キンセラ氏(故人)の言葉「野球場のホームプレートに立ってファウルラインを永遠に延長していくと、世界のほとんどが入ってしまう。そんな神話的レベルの虚構の世界を見せてくれるのが野球なんだ」は宝物となった。以降、2000年代前半まで、メジャーのスプリングトレーニング、公式戦、オールスター、ワールドシリーズを現地取材。現在は『web Sportiva』でヤクルトを中心に取材を続けている。