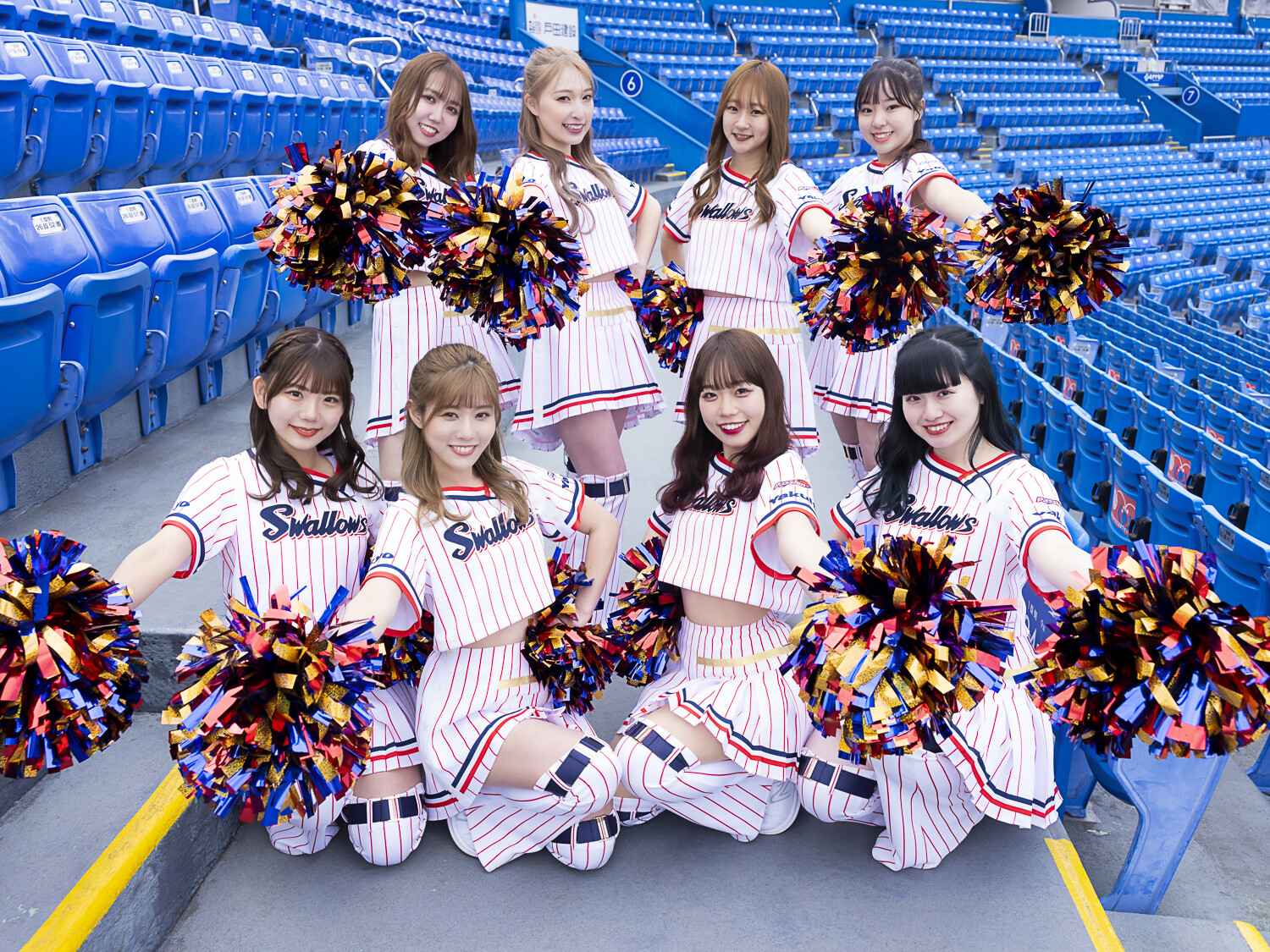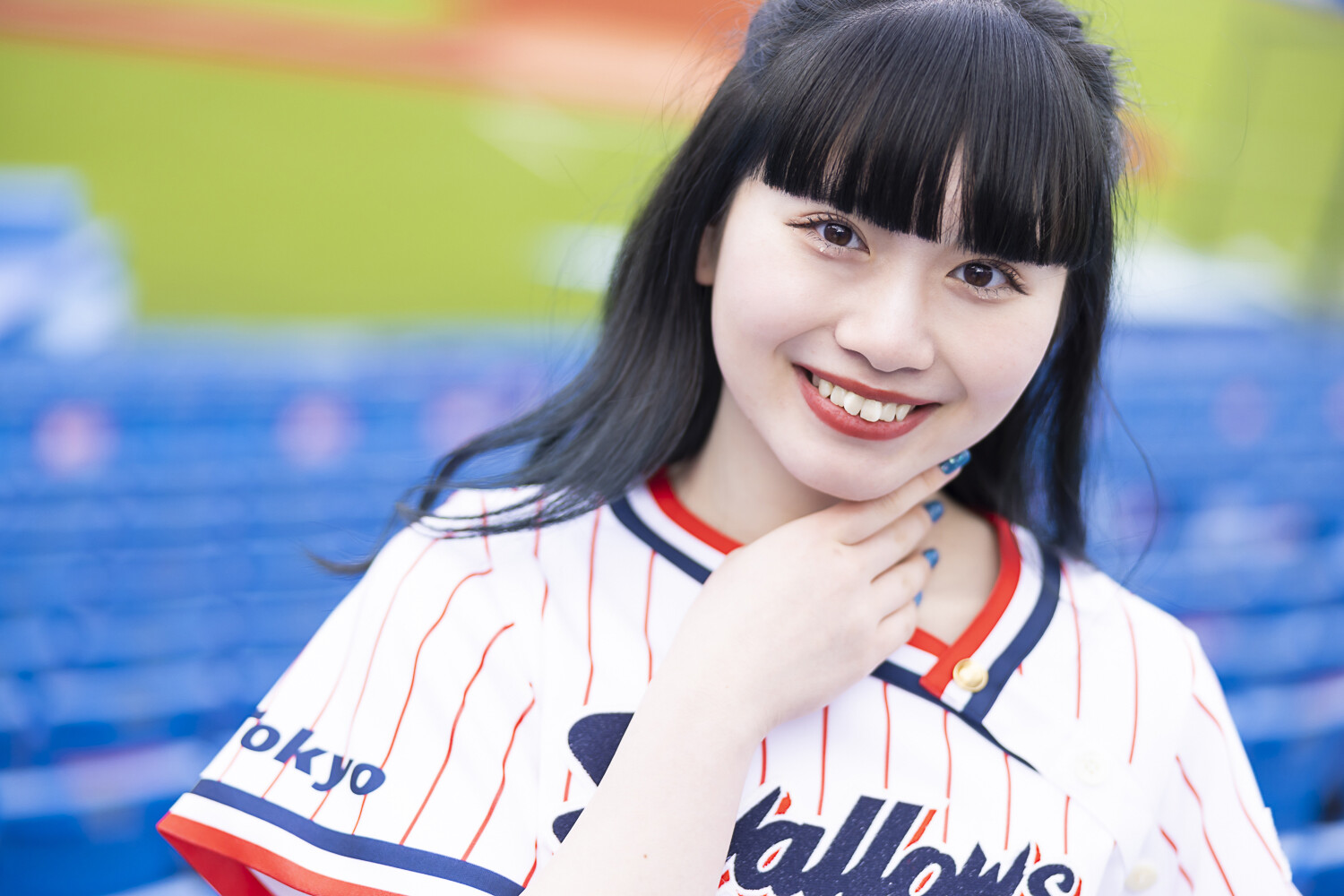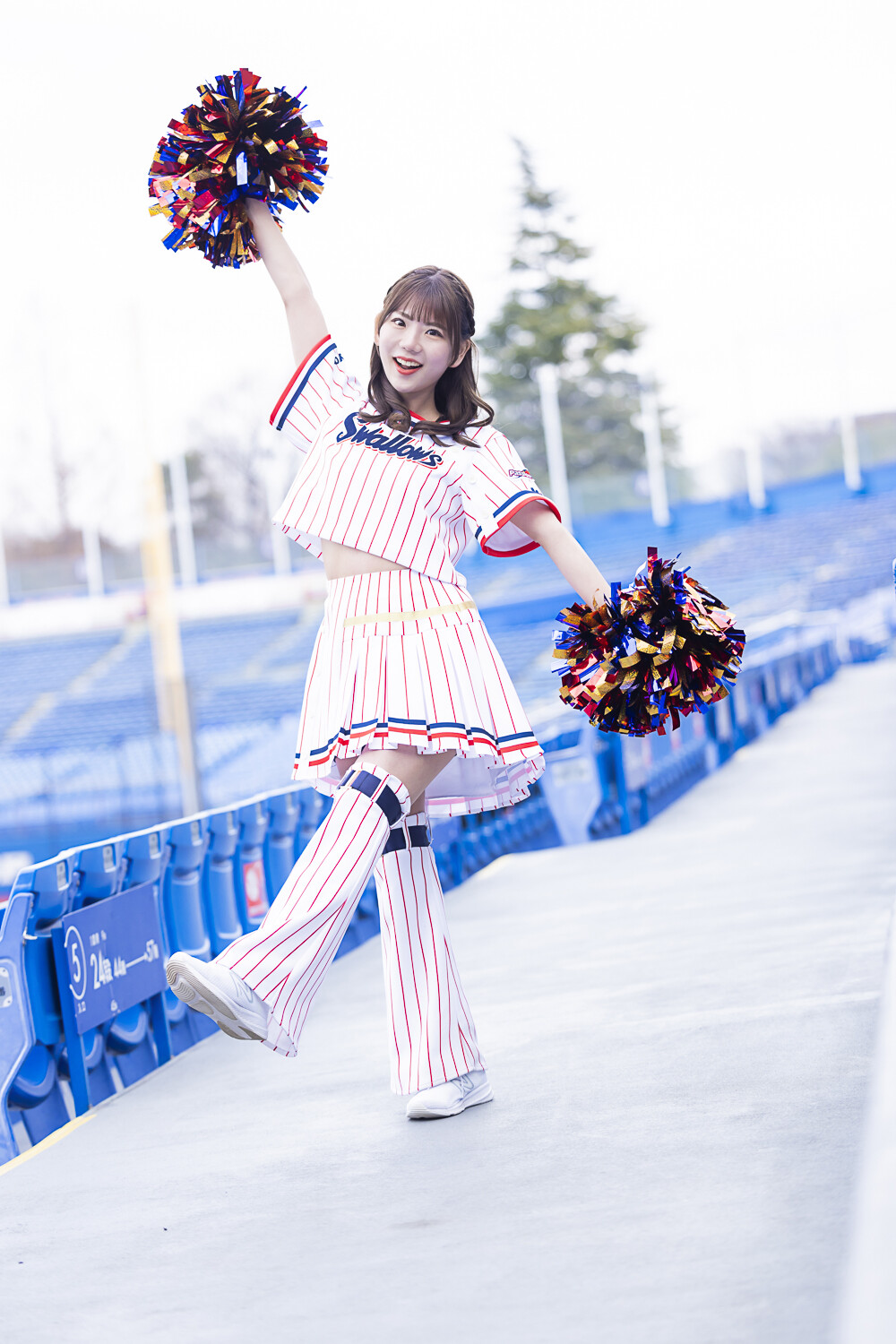ヤクルト「地獄の松山キャンプ」を若手野手陣が完走 限界突破から見えてきた世界とは? (5ページ目)
その中川だが、バットを強く振るということでは大きな成果があったと語る。
「飛距離や打球スピードがあるなというのはアピールできたんですけど、ポテンシャルだけではやっていけない世界なので。まだ実践形式の打撃では、マイナスポイントが多かった。来年はキャッチャーが増える(ドラフトで2人指名)ので、台湾のウインターリーグで挽回して、まずは来年、二軍で試合に出られるように頑張りたいです」
北村恵吾はルーキーイヤーとなった昨年、プロ初本塁打がグランドスラムと派手なデビューを飾ったが、今年は腰のケガなどもあり、一軍出場機会なくシーズンを終えた。
「悔しい結果で終わってしまったので、このキャンプでは何かをやり遂げた自信というか、達成感というものがほしいと毎日やってきました。正直、初日にやり切った感はありましたけど、『うわっ、これを明日も明後日もやるのか』みたいな感じで(笑)」
手のひらはマメが潰れボロボロになり、キャンプ中に行なわれた練習試合では野球人生で初めてテーピングを巻いて出場した。
「数をこなすことで免疫力もつきましたし、疲れたなかでも教えてもらったことが体に染み込んできたと感じられたのはよかったです。気持ちが折れそうな時もありましたけど、最後までやり遂げられたのかなと思っています」
キャンプ最後の"バッティングの日"には、全体練習後、吉岡雄二打撃コーチに"おかわり"をお願いした。キャンプ前半では考えられないことだった。
「この2週間、数を振ってきたことで、今までになかったいい感覚があったんです。少しでも打って、この感覚を忘れたくない、もっと体に染み込ませたい、味わいたいと思って、吉岡コーチにお願いしました」
松山キャンプ打ち上げの日の朝、坊っちゃんスタジアムで体を動かす選手たちの表情はじつに晴れやかだった。大松コーチが言う。
「オフの過ごし方は全選手に伝えてあるので、来年2月、いま以上にパワーアップしたみんなに会えることを楽しみにしています」
"シン地獄の松山キャンプ"から1カ月以上が過ぎた。西村、伊藤、中川は前述のとおり台湾のウインターリーグで実戦経験を積み、北村、橋本、鈴木、高野は戸田球場で連日のように走り込んでいた。ほかの選手たちも各所で、飛躍の来年へ向け動き続けている。
著者プロフィール
島村誠也 (しまむら・せいや)
1967年生まれ。21歳の時に『週刊プレイボーイ』編集部のフリーライター見習いに。1991年に映画『フィールド・オブ・ドリームス』の舞台となった野球場を取材。原作者W・P・キンセラ氏(故人)の言葉「野球場のホームプレートに立ってファウルラインを永遠に延長していくと、世界のほとんどが入ってしまう。そんな神話的レベルの虚構の世界を見せてくれるのが野球なんだ」は宝物となった。以降、2000年代前半まで、メジャーのスプリングトレーニング、公式戦、オールスター、ワールドシリーズを現地取材。現在は『web Sportiva』でヤクルトを中心に取材を続けている。
フォトギャラリーを見る
5 / 5