1984年ロス五輪直前、金メダル候補の瀬古利彦は血尿を出し、泣きながら電話した母親からは「死んだらあかんよ」と言われた (3ページ目)
【ロス五輪2週間前にドクターストップ】
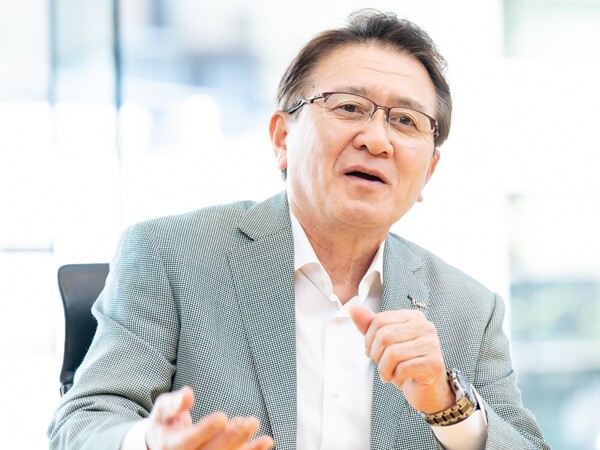 「調子がまったく上がらなかった」と振り返る photo by Sano Miki
「調子がまったく上がらなかった」と振り返る photo by Sano Miki
ロス五輪の1カ月前になっても、瀬古の調子は一向に上がらなかった。練習が終わると、どっしりした重さと疲れがやってくる。
「調子がよくないうえに練習不足だと感じていたので、ロスの暑い気候に合わせて暑い東京で練習をしていたんです。さすがに日中は厳しいので夜6時ぐらいから始めて、40kmを走り終えてから夜ご飯になるんですけど、疲れすぎて食べられないんです。練習を休みたい気持ちもありましたが、監督から『疲れているとか、休みたいとか言ってはいけない』と言われていたので、自分に『大丈夫、大丈夫』と言い聞かせて走っていました」
五輪2週間前には20kmのタイムトライアルを行なった。午後6時、明治神宮外苑の気温は31℃の蒸し暑い夜だった。最初の10kmを31分で走ったが、後半の10kmは36分もかかった。フラフラになり、そのままトイレに行くと、血尿で便器が真っ赤に染まった。さすがに「やばい」と思い、監督に伝え、翌日に病院に行くとドクターストップがかかった。
「医者に走っちゃダメだと言われました。正直、なぜそこまで自分を追い込んでいるのか、なぜそこまでやるのか、自分でもわからなかった。これが五輪というものの正体というか、プレッシャーなのかなと思いましたね」
瀬古は体を休め、負担がかからないようにウォーキングをした。だが、迫ってくる五輪と自分の現状を照らし合わせると、頭はパニック寸前だった。
「誰にもこのことは言えないし、マスコミに話したらえらいことになってしまう。このままだとおかしくなりそうだったので、実家のおふくろに泣きながら電話をしたんです。今の状況を伝えて、『俺は走れない。もう五輪に行けないかもしれない』って。まあ、おふくろはびっくりしますよね。最後に『利彦、お前、死んだらあかんよ』と言われて。その夜、おふくろが心配して会いに来てくれたんです。
そうしたら気持ちがスッと晴れたんです。なんかすごく元気になって、『あっ、これはいける』と思い、栄養ドリンクを飲みながらレース本番4日前に日本を出発しました」
3 / 4


