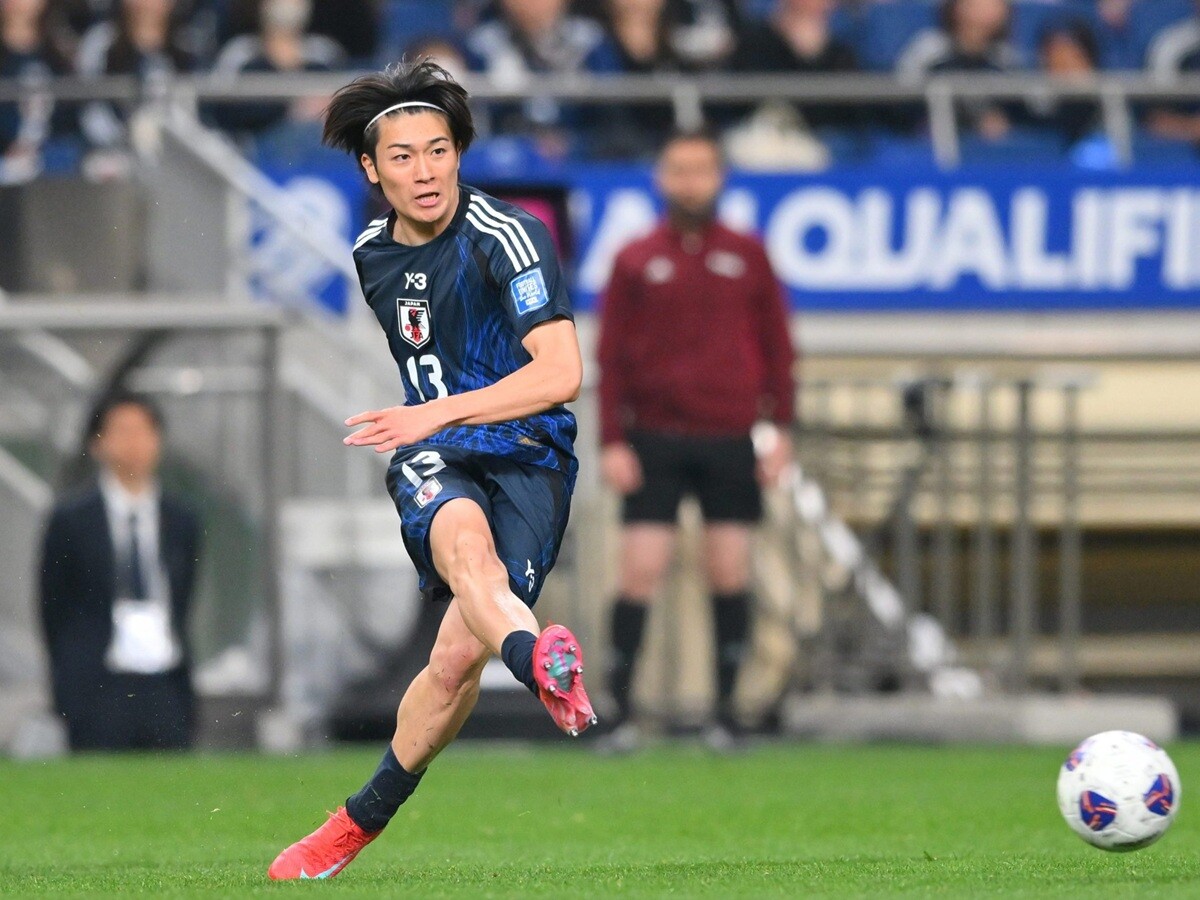バルセロナはチャンピオンズリーグ&ラ・リーガの頂点をつかむか 「背水の陣」を支えるCBコンビの動きを分析 (3ページ目)
【ラインを離脱するイニゴ・マルティネス】
ミランでサッキ監督がプレッシングという新戦術を導入した当初、「バレージは劣等生だった」と述懐している。フランコ・バレージは守備の重鎮、プレッシングとラインコントロールの象徴ともいうべき存在だったので、呑み込みが悪かったというサッキの発言は意外に思ったものだ。
当時、キャプテンのバレージは27歳。CBを組んだアレッサンドロ・コスタクルタは21歳、左サイドバック(SB)パオロ・マルディーニは19歳だった。右SBマウロ・タソッティはバレージと同年齢だったが、素直にサッキ流を吸収した若手と違って、バレージは経験がかえって邪魔になっていたのだろう。ラインコントロールの呑み込みが悪いということは、他の選手と高さが揃わなかったからだ。バレージだけ後方にいたのではないかと想像できる。
バレージは危機察知能力が抜群だった。いち早く「オフサイドにならない」と感知して裏のスペースをカバーする能力は鬼気迫るものがあり、左CBなのに右SBのカバーまで行なっていたものだ。この予知能力と反応の速さが他のDFとラインを揃えるにあたって邪魔になっていたのだろう。しかし、サッキ流に順応してからは、むしろバレージの能力にチームが助けられることになった。
クバルシは18歳、イニゴ・マルティネスは33歳。コスタクルタとバレージの関係に近い。クバルシはハイラインの申し子だが、イニゴは経験でハイラインのバグをカバーしている。
バルセロナはプレッシャーOFFの後退局面でも、あまりFWとの距離に余裕を持たない。FWの能力とパスが出るタイミングしだいでは裏をつかれる危険はあり、実際それで失点もしている。2列目からの飛び出しという、ハイラインの弱点を突いてくるチームもある。イニゴはそれらの被害をある程度にとどめる役割を果たしている。
危ないと感じたら、単独でラインを離脱して後退している。強気に下げないクバルシとは対照的だが、イニゴの好判断で失点を免れる場面もかなりあるのだ。
ちなみにトルシエ監督は後退時の相手FWとの距離を3メートルに設定していた。これだけあれば競走になっても大丈夫ということなのだが、セーフティーすぎてFWの足下に簡単にクサビが入ってしまう欠点があった。バルセロナの後退時の距離感はもっと短い。それだけ裏のリスクを負っている。クバルシとイニゴの個の力でカバーしているとはいえ、それでもリスキーなのは確かである。
ただ、バルセロナは伝統的に攻撃するチームであり、それはクラブのアイデンティティにも関わっている。いわば背水の陣を敷いたようなもので、攻撃への傾斜をより鮮明にしているわけだ。今季ここまで30試合83ゴールはラ・リーガでダントツ。リスクを負っただけの成果は出ている。
著者プロフィール
西部謙司 (にしべ・けんじ)
1962年、東京生まれ。サッカー専門誌「ストライカー」の編集記者を経て2002年からフリーランスに。「戦術リストランテ」「Jリーグ新戦術レポート」などシリーズ化している著作のほか、「サッカー 止める蹴る解剖図鑑」(風間八宏著)などの構成も手掛ける。ジェフユナイテッド千葉を追った「犬の生活」、「Jリーグ戦術ラボ」のWEB連載を継続中。
【写真&選手紹介】現在の世界トップレベル ワールドサッカー「新」スター名鑑
3 / 3