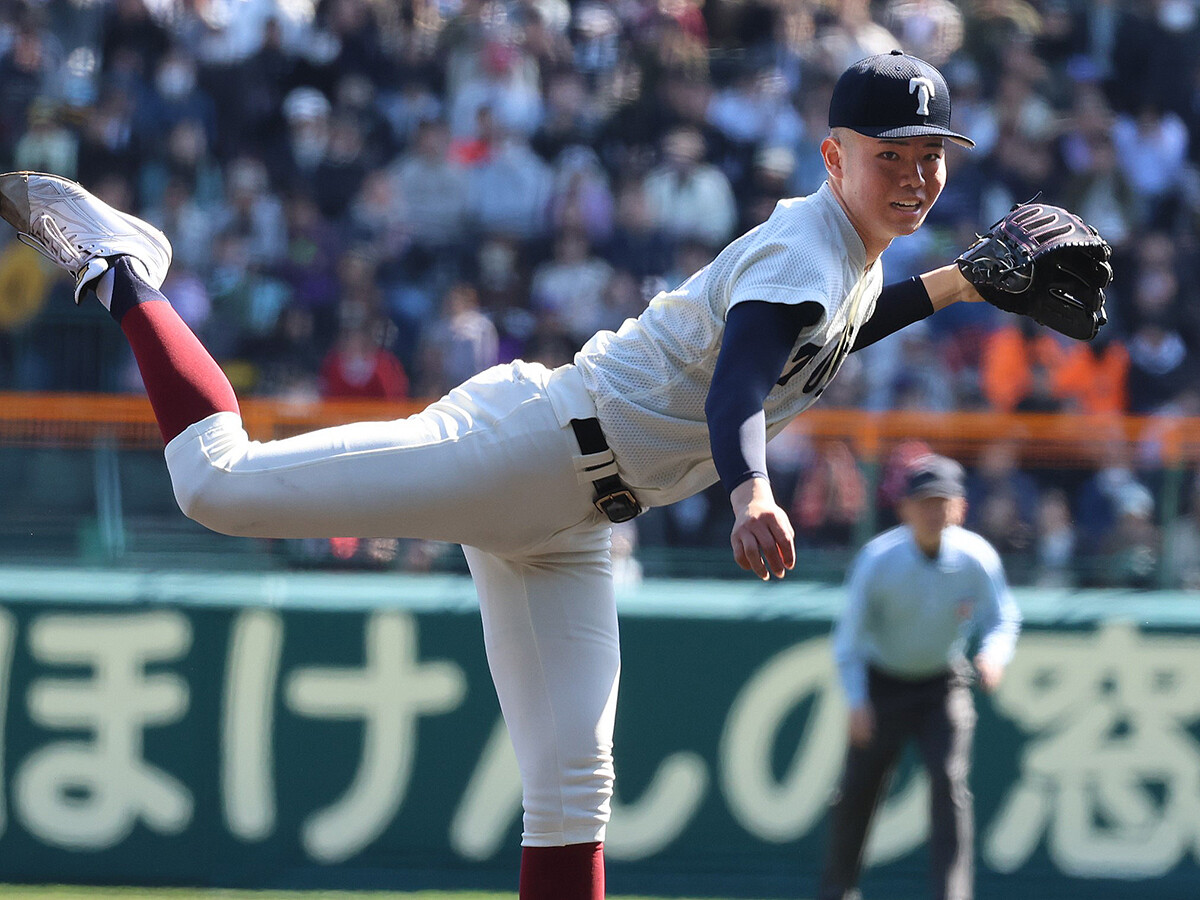【夏の甲子園】「大社旋風」は必然だった⁉︎ 選手主導の戦いが示した高校野球の新しい形 (3ページ目)
じつはこの時、早稲田実業の内野手は10回表の大社と同じようにピックオフプレーを仕掛けている。しかし投手がボールを投げてしまい、失敗に終わっている。このプレーを成功させるのがいかに難しいのかがわかるシーンだった。
バントシフトが緩くなったところで、安松は三塁線に絶妙なバントを成功(結果は内野安打)させた。無死満塁となったところで、真庭がセンター前へ弾き返し、大社が勝利した。
投げる、打つ、走るといったレベルはもちろん、どうやって得点を挙げていくか、失点を防いでいくかといった戦い方がチームとして整理されていた。つまり、大社は甲子園で勝つための準備をしていた。しかも、それらが監督ではなく選手たち主導で行なっていたところに、このチームの強さがある。
石飛監督は言う。
「どう守るか、どう点を取るかは、選手と一緒に相談しながらやっています。ただその意見交換というのは、状況などを考えて、まず選手たちで話し合います。そこに僕が入る感じで、選手たちの話を聞きながら、迷っている選手がいれば声をかけます。(早実戦の)代打バントの時もそうです。立候補があって、『オレはいけると思う。どうだ?』っていうような会話がありました」
大社ナインの思い切ったプレーは、監督の指示のもとに動くのはなく、選手自らが決めて実行しているところがベースにある。
甲子園での戦いを振り返り、石飛監督に「3つの勝利で見えたものは何か?」と問うと、こんな答えが返ってきた。
「やはり目標に対して、ブレずにいることだと思います。そして、その目標に対して現在地がどこで、何が足りなくて、これからどうしていけばいいのか......それを主体的に考えて行動すること。これは間違っていなかったと思います。選手がどうしたいか、チームとしてどうしたいか、これを常に問いながらやっています。そのなかでリーダーシップのあるキャプテンの石原や、ショートの藤江(龍之介)が引っ張ってくれました。選手の主体的な取り組みには手応えがあります」
これまで高校野球、なかでも甲子園に出場するようなチームは、指揮官の力によるところが大きかった。しかしこの夏、大社が実践した選手主導の戦いは、新たな高校野球の可能性を示したと言えるだろう。
著者プロフィール
氏原英明 (うじはら・ひであき)
1977年生まれ。大学を卒業後に地方新聞社勤務を経て2003年に独立。高校野球からプロ野球メジャーリーグまでを取材。取材した選手の成長を追い、日本の育成について考察。著書に『甲子園という病』(新潮新書)『アスリートたちの限界突破』(青志社)がある。音声アプリVoicyのパーソナリティ(https://voicy.jp/channel/2266/657968)をつとめ、パ・リーグ応援マガジン『PLジャーナル限界突パ』(https://www7.targma.jp/genkaitoppa/)を発行している
フォトギャラリーを見る
3 / 3