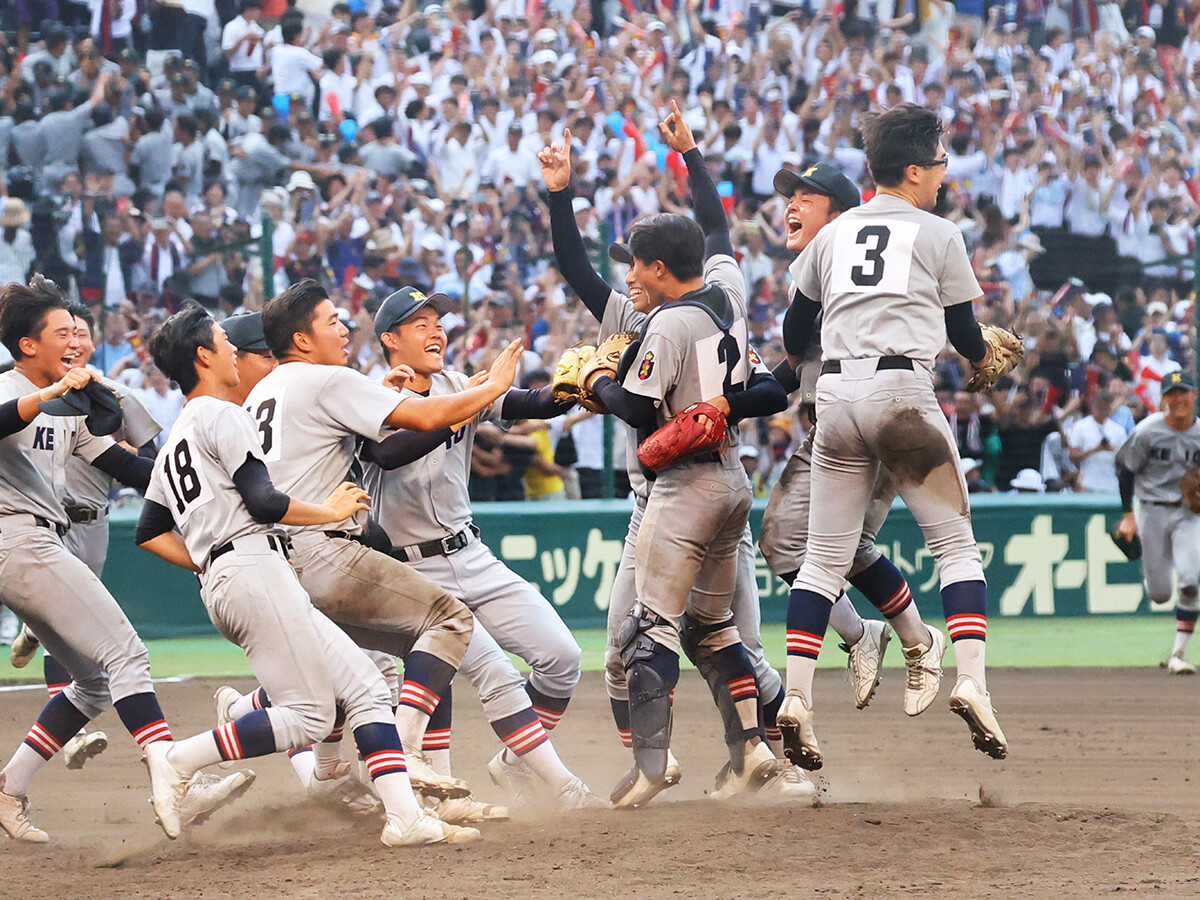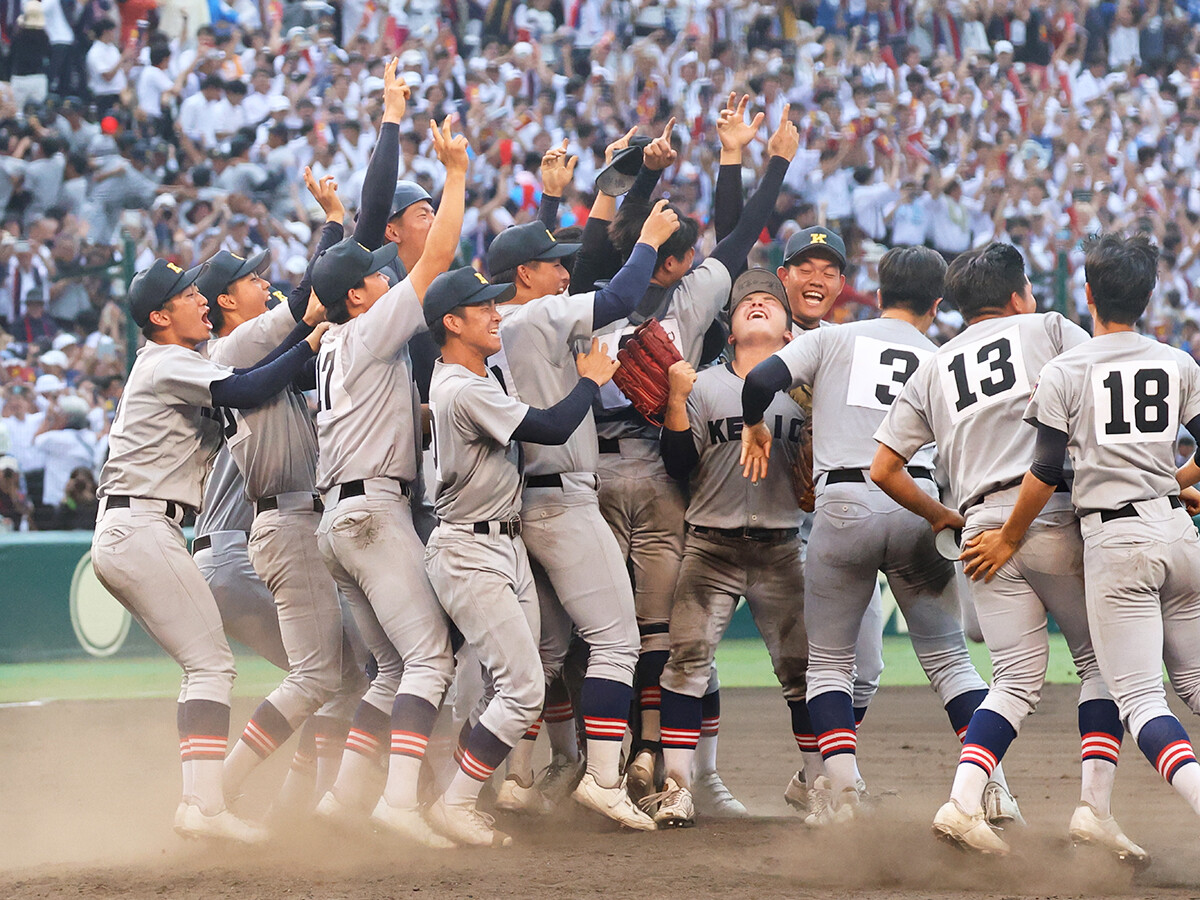慶應高校&慶應大が力を発揮するために取り組むミーティングと土台にある野村克也の言葉
4季ぶりの優勝を目指す東京六大学・秋季リーグの開幕2日前の9月7日、練習を終えた夕刻、慶應義塾大学野球部の下田グラウンドでは約180人の部員が外野の人工芝に集まっていた。就職活動などで来られない者を除き、選手、マネジャー、アナリストらチーム全員が一同に会している。
「毎月、この予定を最初に立てます。リーグ戦と同等の重みを置いているんです」
2019年12月から母校を率いる堀井哲也監督がそう話したのは『木鶏会(もっけいかい)』と呼ばれるミーティングの取り組みだ。各業界で成功を収めている者たちが体験談や考え方を読み、感想文をまとめて4人1組で発表し合う。そして6人程度の代表者が前に出て、部員全員の前で、グループで話し合ったことを伝えていく。
 慶應大で行なわれたミーティングの様子この記事に関連する写真を見る
慶應大で行なわれたミーティングの様子この記事に関連する写真を見る
【チームでコミュニケーションを図る】
慶應大でこの取り組みが始まったのは、現在トヨタ自動車でプレーする福井章吾がキャプテンだった頃、チームをまとめ上げるのに苦労している姿を見て、堀井監督が提案したことがきっかけだ。
堀井監督は社会人野球の監督時代からマネジメント法を勉強し、都市対抗優勝や数々のプロ野球選手の輩出につなげてきた。母校の慶應大学で監督に就任して以降、育成とともに重きを置くのが教育だ。その意味で、この会には2つの利点があると言う。
「我々指導者が選手に伝えたいことは、結局、先人や成功者、リーダーの言葉と共通しています。選手たちはそうした言葉を読み、自分で書いて発表する。インプット、アウトプットが同時にされることがひとつですね。
また、学年や、レギュラーか控え、マネジャーも選手も関係なく、みんなで話し合います。200人も部員がいる集団の場合、話す機会のないまま1年間が終わる人もいると思います。そうなることを比較的解消でき、チームでコミュニケーションを図ることができる。この2つが大きいですね」
学生たちの発表を聞きながら、堀井監督は気になった言葉をメモしていく。手に持つノートには、過去に選手たちが発表した言葉がいくつも書かれていた。
1 / 3
著者プロフィール
中島大輔 (なかじま・だいすけ)
2005年から英国で4年間、当時セルティックの中村俊輔を密着取材。帰国後は主に野球を取材。新著に『山本由伸 常識を変える投球術』。『中南米野球はなぜ強いのか』で第28回ミズノスポーツライター賞の優秀賞。内海哲也『プライド 史上4人目、連続最多勝左腕のマウンド人生』では構成を担当。