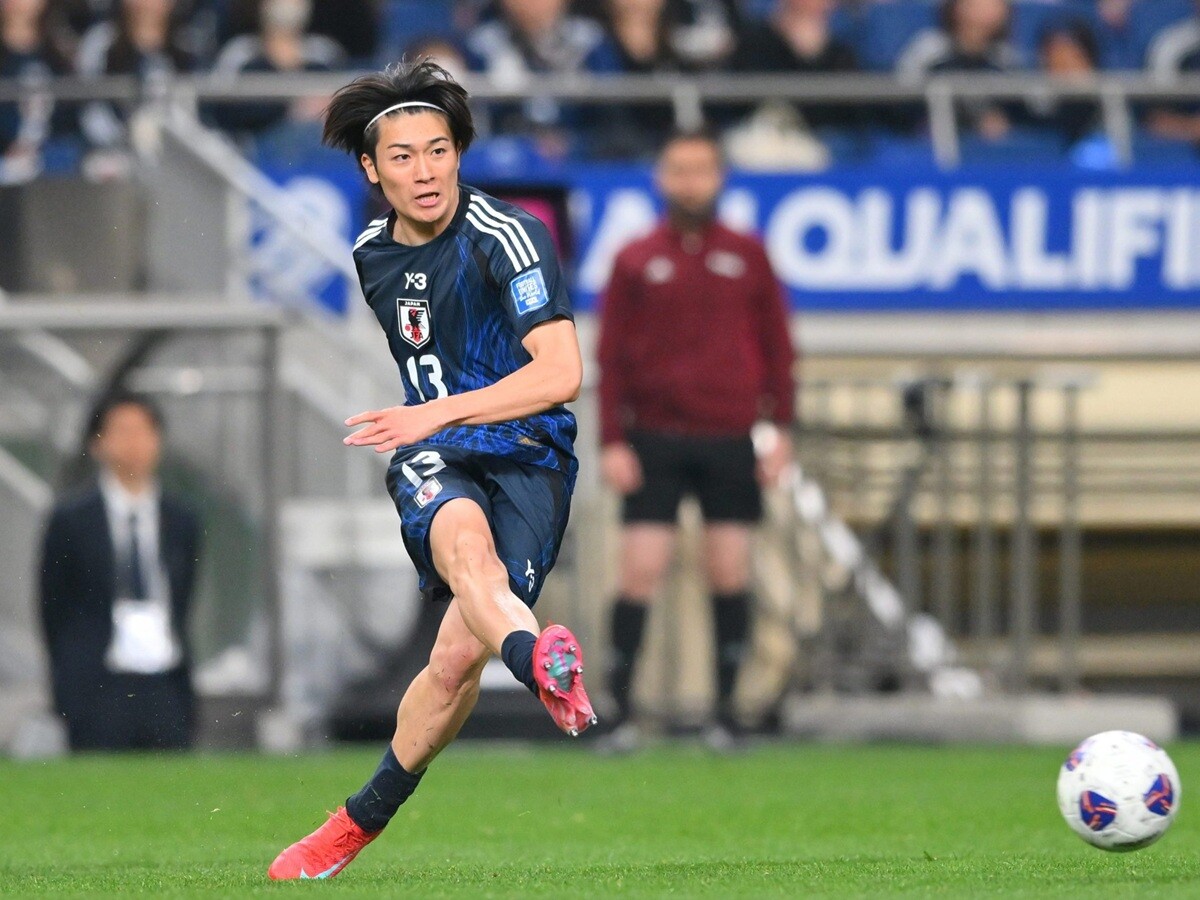サッカー日本代表の問題解決に重要な「プレーメーカー」の存在 世界最高峰はポルトガルにいる (3ページ目)
【後方で活路を拓き、守備もやる】
パリSGでのデビュー戦となったナント戦で、ヴィティーニャは43本のパスをすべて通し、パス成功率100%というスタッツだった。この試合だけでなく、パスミスは非常に少ない。いったん触れたボールを失うことも少ない。キープ力、配球力が抜群。
カテゴライズすればディープ・ライング・プレーメーカー。アンドレア・ピルロが代表的だが、中盤の底に守備型の選手しか配置してこなかった時期が長すぎたので、ピルロの起用が新機軸と言われたのだが、もともとプレーメーカーは深い位置からプレーするものだった。
守備型MFが中央に配置されていたのは、そこが守備の重要地域だから。ボールアーティストを置く余裕はなく、プレーメーカーの居場所が消滅しそうな時期は確かにあったわけだ。ピルロや、それ以前のジョゼップ・グアルディオラ、フェルナンド・レドンドなどが深い位置にプレーメーカーを置く有効性を証明したことでプレーメーカーが復権していった経緯がある。
ポルトガルはエウゼビオ、クリスティアーノ・ロナウドの破格のゴールゲッターを輩出した国だが、意外と名CFは少なく、ウイングとセンターバック、MFに関しては切れ目なくハイレベルの人材を生み出している。現在もMFにはベルナルド・シウバ、ブルーノ・フェルナンデスがいて、ヴィティーニャは先輩ジョアン・モウチーニョの正統後継者だ。
テクニックと頭脳で勝負のヴィティーニャだが守備力もある。古典的なプレーメーカーだが、それだけではないところが現代サッカーで生き抜けるポイントかもしれない。
芯を食った右足のミドルシュートを持ち、ドリブルもうまい。攻撃的MFでも十分やれる。ヴィティーニャは「小さなジダン」だが、ジダンのサイズがないのでポジションが後方になっているのだと思う。相手とコンタクトしない俊敏さとスキルがあるとはいえ、ポジションが前になるほどマークされコンタクトも避けられなくなるからだ。ピルロも同じ理由でポジションを下げた。下がった以上は守備もできなければならない。
日本は技術に優れて俊敏な攻撃的MFを多数輩出する土壌があるが、そのまま世界トップで活躍するのは難しい。体格の不利があるからだが、ヴィティーニャのように後方で活路を拓ける可能性はある。そこでポイントになるのは守備力だ。そこさえクリアできれば、日本人プレーメーカーが欧州で一気に増加するのではないかと思う。
著者プロフィール
西部謙司 (にしべ・けんじ)
1962年、東京生まれ。サッカー専門誌「ストライカー」の編集記者を経て2002年からフリーランスに。「戦術リストランテ」「Jリーグ新戦術レポート」などシリーズ化している著作のほか、「サッカー 止める蹴る解剖図鑑」(風間八宏著)などの構成も手掛ける。ジェフユナイテッド千葉を追った「犬の生活」、「Jリーグ戦術ラボ」のWEB連載を継続中。
【写真&選手紹介】ワールドサッカー「新」スター名鑑 世界トップクラスの選手たち
3 / 3