小説『アイスリンクの導き』第2話 「原点回帰」 (3ページ目)
「世界中の人に、あなたのスケートを見せましょう!」
全国から有望な子供スケーターが集められた野岳山での合宿の後、波多野に声を掛けられた時、翔平は半信半疑だった。
「僕は凌太じゃないですよ」
念のために断った。当時、凌太は次世代の強化トップ選手だったのだ。
「もちろん、知ってるわ」
「僕はあいつのように滑れません」
翔平は言った。
「今のところは、凌太君の方が上ね。でも、あなたは滑るのが好きでしょ? 練習が嫌いじゃない」
「練習は、好きです」
そう言うと、波多野は「今は分からなくていいわ。自分のスケートを信じ、練習するだけで。練習好きは才能よ」と言ってくれた。翔平は、それを聞いてどれだけ励まされたか。波多野がコーチでなかったら、道に迷っていたかもしれない。
波多野は翔平の才能に惚れ込んでいたからこそ、大阪の自宅に住み込みのような形にし、徹底的に鍛えてくれた。二人三脚で、目覚ましい成長だった。そんな彼女は病魔に襲われ、翔平を残して他界した。しかし、その遺志が膝のケガをも乗り越えさせたのだ。
〈自分もいつか、波多野先生のような存在にこれからなるべきなのかな〉
翔平はぼんやりと思うこともあった。子供たちが無邪気にスケートに挑む姿を見ていると、指導者も悪くないかも知れない。
一方で、もう一つの気持ちも消えず、持て余すほどに大きくなってしまった。
〈まだ、選手として滑りたい。もう一度、滑ることができるんじゃないか〉
甘いと言われるかもしれないが、その欲がいくら打ち消しても膨れ上がってくる。
目の前のリンクでは、5分間の休憩に入っていた。何度も転んだ小さな少年が、お母さんに抱きついて泣いているようだった。よしよし、と労われると、不甲斐なさや痛みや怖さがないまぜになるのか、混乱してさらに大声で泣き出した。さながら、ソロライブステージだった。
「スケートを嫌いになって欲しくないな」
翔平は小さな声で呟いた。みんなリンクサイドで休憩に入って、リンクには一人で立っていた。頭の中に曲が鳴り響いた気がする。体は自然に動き出していた。ミラノ五輪や世界選手権を制した「道」の最後のストレートラインステップ、「自分だけが知る楽しい瞬間を糧に、人は生きていける」という思いを、少年に見せてあげたい衝動で滑った。
前髪が靡いて景色が後ろに流れる。エッジを倒し、上体をかぶせ、そこから跳ね上がる。こんな道もあるんだよ、という一心で、主人公ジェルソミーナの喜怒哀楽を全身で表現した。自分とも重なる人生の賛歌を、泣きじゃくる彼にもそれを伝えたかった。幼すぎて、言葉では通じ合えないからこそ、ステップからスピンまでの数十秒間を"永遠の一瞬"に閉じ込めた。
気づくと、会場では大きな拍手喝采が起きていた。小さな少年はすっかり泣き止んでいた。大人たちの中には、涙を流している人までいるようだった。リンクサイドで見ていた凌太は少し苦笑いだったけど、優しい表情を浮かべていた。
「あなたは本当に楽しそうに滑る。楽しさを人に伝えられるのは、神様からもらった贈り物。見ている人が、自然と幸せになるの。だから、才能を決して無駄にしないで」
波多野の言葉が脳裏に響く。
翔平は拍手を浴びながら、体裁が悪くなって頭をかいた。でも、再びリンクに上がった少年を見て、踊りきったことに後悔はなかった。
揺れていた自分の気持ちが、定まってきたことを感じていた。
(つづく)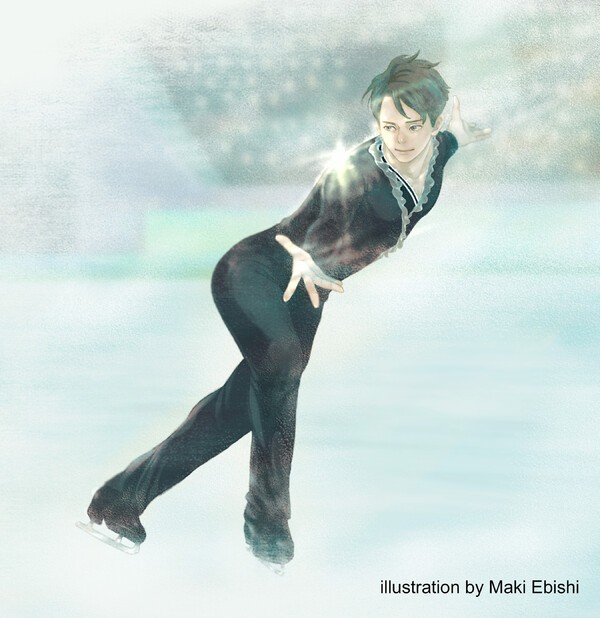
著者プロフィール

小宮良之 (こみやよしゆき)
スポーツライター。1972年生まれ、横浜出身。大学卒業後にバルセロナに渡り、スポーツライターに。語学力を駆使して五輪、W杯を現地取材後、06年に帰国。著書は20冊以上で『導かれし者』(角川文庫)、『アンチ・ドロップアウト』(集英社)など。『ラストシュート 絆を忘れない』(角川文庫)で小説家デビューし、2020年12月には『氷上のフェニックス』(角川文庫)を刊行。パリ五輪ではバレーボールを中心に取材。
3 / 3


