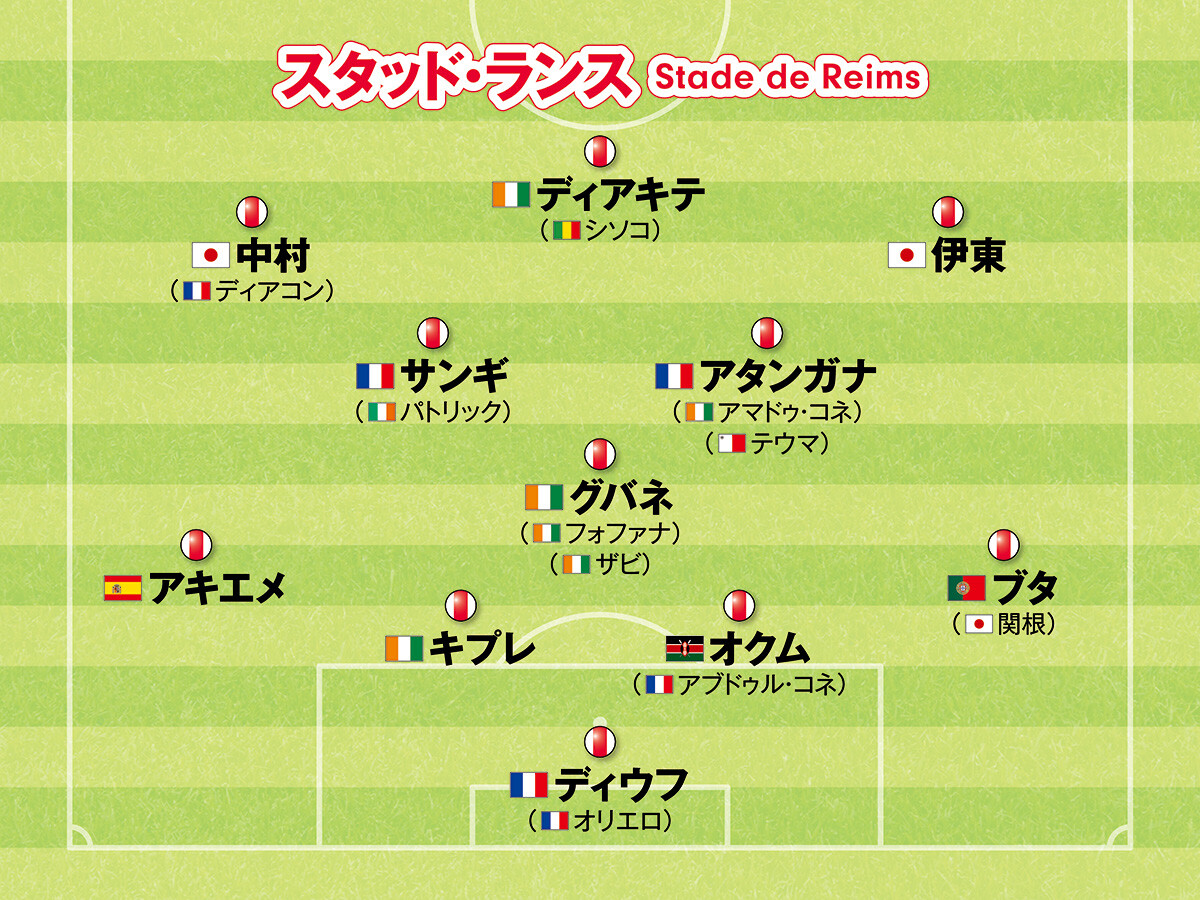チャンピオンズリーグでインテルがじわりと存在感 3-5-2を機能させる2トップの強さ
この続きはcodocで購読
西部謙司が考察 サッカースターのセオリー
著者プロフィール
西部謙司 (にしべ・けんじ)
1962年、東京生まれ。サッカー専門誌「ストライカー」の編集記者を経て2002年からフリーランスに。「戦術リストランテ」「Jリーグ新戦術レポート」などシリーズ化している著作のほか、「サッカー 止める蹴る解剖図鑑」(風間八宏著)などの構成も手掛ける。ジェフユナイテッド千葉を追った「犬の生活」、「Jリーグ戦術ラボ」のWEB連載を継続中。