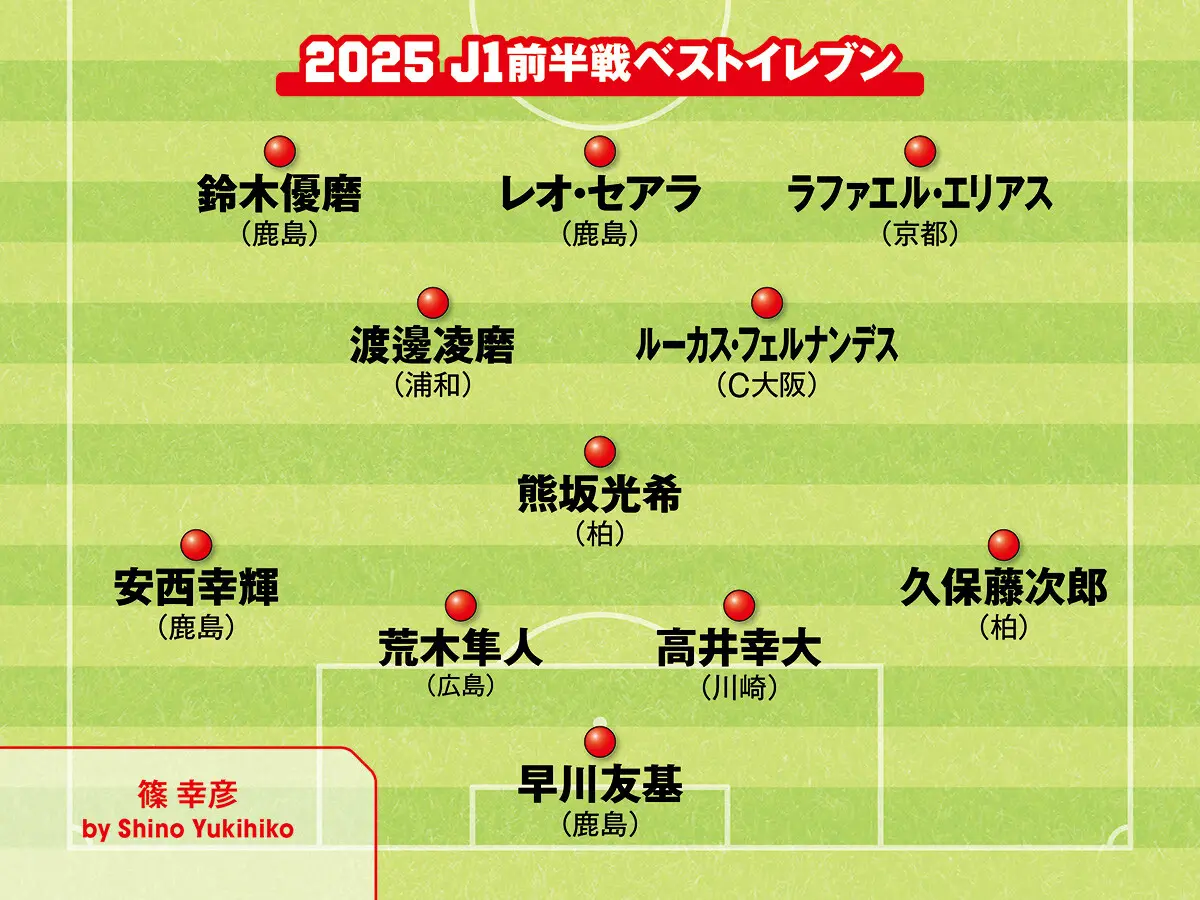【Jリーグ連載】東京ヴェルディ・アカデミーがプロで活躍する選手を輩出し続けているのはなぜか (2ページ目)
だが、1993年にJリーグが創設されると、Jクラブにアカデミーの保有が義務づけられたこともあり、全国各地に充実した環境を備えるクラブチームが誕生。高校サッカーとは別に、クラブユースが新たな潮流として拡大・発展していくなかで、ヴェルディユースの存在は次第に特別なものではなくなっていく。
加えて、ヴェルディはトップチームが2006年にJ2降格。2008年に一度はJ1復帰を果たすも、1シーズンで再びJ2降格となると、以降2023年までJ2から抜け出すことができず、J2ですらふた桁順位に甘んじることも少なくなかった。
近年、ヴェルディユースを取り巻く環境は、1990年代以前とは明らかに異なるものに変わっていたのである。
とはいえ、Jユースカップで頂点に立てなかった27年間、あるいは、高円宮杯U-18プレミアリーグから遠ざかった10年間、ヴェルディユースは必ずしも低迷していたわけではない。
Jクラブのユースチームには、大会で好成績を残す以上に、プロ選手を育てるという重要な使命があるが、ヴェルディユースはタイトルから遠ざかった時期も、トップチームがJ2で苦しんでいた時期も、コンスタントにプロで活躍する選手を輩出し続けていたからだ。
記憶に新しいところでは、2024年パリ五輪に出場したU-23日本代表でダブルボランチを組んだ、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ/ドイツ)と山本理仁(シント・トロイデン/ベルギー)は、そろってヴェルディユース出身。その他、中島翔哉(浦和レッズ)、畠中槙之助(セレッソ大阪)、渡辺皓太(横浜F・マリノス)、前田直輝、井上潮音(ともにサンフレッチェ広島)らは皆、ヴェルディユースで腕を磨いた選手たちであり、彼らはJ2時代のトップチームでプロデビューを果たし、その後、J1クラブに引き抜かれた才能である。
現在の日本代表(A代表)を見ても、川崎フロンターレ、浦和レッズ、ガンバ大阪など、Jクラブのアカデミー出身者は数多いが、そのほとんどがJ1クラブだ。ヴェルディのように、これだけトップチームが長い間J2にいながら、J1クラブに勝るとも劣らない育成力を発揮してきたクラブは、極めて稀であるばかりか、驚異的ですらある。
ヴェルディユースが、かつてはクラブユースを代表するブランドであり、技術重視のイメージを確立していたと言っても、それは数十年も昔の話。そんな時代を知らない10代の子どもたちが進路選択に際し、今まさに強いJ1クラブの育成組織に入りたいと憧れたとしても不思議はない。
つまりは、アカデミーの人材獲得競争においても、ヴェルディは長らく不利な状況にあったはずなのである。
にもかかわらず、なぜヴェルディは、これほどまでにプロで通用する人材を育て続けられるのだろうか。
「ここ2、3 年で言うと、トップチームの躍進が大きいかなと思います」
そう語るのは、自身も読売ユースの出身で、現在はヴェルディのアカデミーでヘッドオブコーチングを務める、中村忠である。
フォトギャラリーを見る
2 / 2